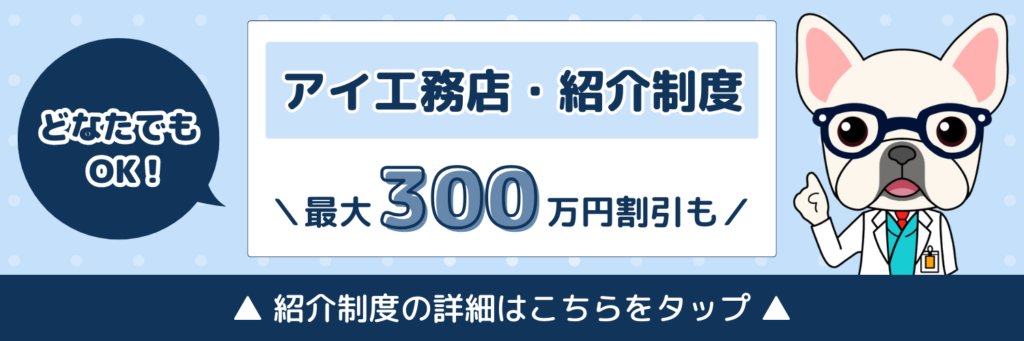- ハウスメーカーは儲けすぎ?一軒の家でどれくらい利益を得ているの?
- 積水ハウスや住友林業、一条工務店の利益率はどのくらい?
- 建売住宅やリフォーム、下請け業者の利益率も知りたい!
実は、ハウスメーカーの利益率は業態や工法、地域によって大きく異なります。大手ハウスメーカーの粗利率は25~35%程度と言われていますが、最終的な営業利益率は5~10%程度にとどまることが多いのです。
なぜなら、広告宣伝費や住宅展示場の維持費、アフターサービスなど、見えないコストも多く存在するからです。また、ハウスメーカーの原価率は50~60%程度で、残りが利益や経費として計上されています。
- ハウスメーカーの利益構造と一軒あたりの利益の仕組み
- 積水ハウス、住友林業、一条工務店の利益率と経営戦略
- 建売住宅、下請け業者、リフォーム事業の利益率比較
- 工法や地域による利益率の違いと家づくりで失敗しないためのポイント
この記事を読むと、住宅業界の利益率の実態を理解し、家づくりにおいて賢い選択ができるようになります。高すぎる利益率は消費者にとって不利な価格設定の可能性がありますが、低すぎると企業の経営が厳しくなり、アフターサービスなどに影響が出る恐れもあります。
 りけお
りけおそれでは、ハウスメーカーの利益率の実態と家づくりの選択肢について詳しく見ていきましょう。
ハウスメーカーの利益率から見る住宅業界の実態


住宅購入を検討する際、気になるのがハウスメーカーの利益率です。家づくりにおける費用の内訳や、各社の経営状況を知ることで、より賢い選択ができるようになるでしょう。
- ハウスメーカーは儲けすぎ?業界の利益構造を解説
- ハウスメーカーが一軒の家で得る利益の仕組み
- ハウスメーカーの粗利率はどのくらい?相場を解説
- ハウスメーカーの原価率と価格設定の関係性
- 積水ハウスの利益率から見る大手の経営状況
- 住友林業の利益率と経営戦略の特徴
- 一条工務店の利益率と高品質住宅の両立方法
ハウスメーカーは儲けすぎ?業界の利益構造を解説
- 大手ハウスメーカーの営業利益率:5~15%
- 工務店の営業利益率:3~5%程度
- 鉄骨系ハウスメーカーの利益率が比較的高い
住宅業界における利益率は企業規模や構法によって大きく異なります。大手ハウスメーカーの営業利益率は一般的に5~15%程度と言われています。一方、中小規模の工務店では3~5%程度と低めの傾向があります。
興味深いのは、構法による利益率の違いです。鉄骨系ハウスメーカーは木造系に比べて利益率が高い傾向があります。例えば、積水ハウスやヘーベルハウスなどの鉄骨系メーカーは上位にランクインしていることが多いです。鉄骨の原材料費が高いため、販売価格も比較的高額になり、結果として利益率も高くなる傾向があります。
しかし、営業利益率が高いからといって「儲けすぎ」と単純に判断するのは適切ではありません。広告宣伝費、住宅展示場の維持費、アフターサービスなど、見えないコストも多く存在するためです。最終的な純利益率は営業利益率よりもさらに低くなることが一般的です。



ハウスメーカーが一軒の家で得る利益の仕組み


- 一軒あたりの利益率:15~40%
- 3000万円の住宅の場合:450万~1200万円の利益
- 利益の使われ方:広告費、展示場維持費、人件費など
ハウスメーカーが一軒の家から得る利益率は、企業によって大きく異なります。一般的に一軒あたりの利益率は15%から40%程度とされています。例えば、住宅価格が3000万円の場合、15%の利益率なら450万円、40%なら1200万円が利益となる計算です。
この利益はどのように使われるのでしょうか。大手ハウスメーカーでは、タレントを起用したCMなどの広告宣伝費に多額の費用を投じています。また、住宅展示場の維持費や地盤調査、土地の測量などの無料サービス、モデルハウスの建設・維持費用なども利益から捻出されています。
住宅業界の最終的な営業利益率は意外と低く、大手ハウスメーカーでも5~10%程度にとどまることが多いです。粗利益から広告宣伝費や住宅展示場、事務所、車両等の経費、従業員の給料、アフターサービス費用などを差し引くと、残る利益は決して大きくありません。競合による値引きや資材高騰があれば、さらに利益は圧迫されます。



ハウスメーカーの粗利率はどのくらい?相場を解説
- 大手ハウスメーカー:25~35%
- 工務店:20~35%
- リフォーム業界:30%前後
住宅業界における粗利率(粗利益率)は、企業の規模や業態によって異なります。大手ハウスメーカーの粗利率は一般的に25~35%程度と言われています。例えば3000万円の住宅を販売した場合、粗利率が30%であれば900万円が粗利益となる計算です。
一方、地域密着型の工務店では粗利率が20~35%程度と言われており、大手ハウスメーカーよりも低めの傾向があります。これは、広告費や展示場の維持費が少ない分、価格が抑えられているためです。ただし、工務店でも経営を安定させるためには一定の利益率確保が必要です。
リフォーム業界に目を向けると、適正な利益率は30%前後と言われています。リフォーム工事は新築と比べて小規模な工事が多く、職人への施工費が高くなりがちです。また、営業や設計、施工管理にかかる社内経費も新築より多くかかるため、利益率が20%を下回ると赤字になるリスクが高まります。



ハウスメーカーの原価率と価格設定の関係性


- 原価率:大手ハウスメーカーで50~60%
- 工務店の原価率:65~75%
- 価格設定の仕組み:利益率を基準に逆算
住宅業界では、家の価格設定において原価率が重要な指標となっています。大手ハウスメーカーの原価率は一般的に50~60%程度とされています。つまり、販売価格の約半分が原価で、残りの40~50%が利益や営業費用となっています。
一方、工務店の原価率は65~75%程度と高めで、利益率は相対的に低くなります。例えば、3000万円の注文住宅を建てる場合、ハウスメーカーの実際の原価は1500万円~1800万円程度であり、残りの1200万円~1500万円がハウスメーカーの利益や経費として計上される計算になります。
住宅購入で損をしないためには、かかった費用ではなく原価で考えることが大切です。ハウスメーカーや工務店によって原価率は異なるため、複数の会社を比較検討し、提供されるサービスや品質と価格のバランスを見極めることが重要です。高すぎる利益率は消費者にとって不利な価格設定の可能性がありますが、低すぎると企業の経営が厳しくなり、アフターサービスなどに影響が出る恐れもあります。



積水ハウスの利益率から見る大手の経営状況
- 売上高総利益率(粗利益率):約20%前後で安定
- 売上高営業利益率:8~9%台で推移
- 売上高純利益率:近年は6%台まで向上
積水ハウスの財務データから、大手ハウスメーカーの経営状況を読み解くことができます。積水ハウスの売上高総利益率(粗利益率)は、2009年から2024年までの期間、概ね19~21%の範囲で安定しています。2010年に一時的に11.55%まで落ち込んだものの、その後は20%前後で推移しています。
売上高営業利益率に目を向けると、2010年に-2.86%と赤字を記録した後、徐々に回復し、近年は8~9%台で安定しています。2017年には9.09%まで上昇し、その後も8%台後半を維持しています。これは住宅業界の中でも高水準と言えるでしょう。
さらに、売上高純利益率は2009年の0.76%から大きく改善し、2024年には6.51%まで向上しています。この数字は、効率的な経営が行われていることを示しています。積水ハウスの利益率の推移は、大手ハウスメーカーの経営状況が総じて安定していることを表しており、高品質な住宅提供と収益性の両立に成功していると言えます。



住友林業の利益率と経営戦略の特徴


- 2025年3月期第3四半期:経常利益43.5%増
- 国内住宅事業:価格改定による利益率改善
- 米国戸建住宅事業:販売単価10.5%増、戸数17.0%増
住友林業の経営状況からは、大手住宅メーカーの戦略が見えてきます。2025年3月期第3四半期決算では、売上高が前年同期比21%増の1兆4923億円、経常利益は43.5%増の1429億円と好調な業績を記録しています。
国内住宅事業では、高価格帯の商品や企画型住宅「フォレストセレクション」の受注獲得に注力しています。価格改定効果による利益率の改善や高付加価値提案により、受注・販売単価が上昇しました。住宅事業の売上高は3815億円(前年同期比1.3%減)でしたが、経常利益は224億円(同2.0%増)と利益率が改善しています。
特筆すべきは米国戸建住宅事業の好調さです。販売単価が10.5%増、戸数が17.0%増、金額が29.4%増と大きく伸長し、利益率も通期計画を上回りました。住友林業の経営戦略は、国内では価格帯別の販売施策を進めて受注獲得を図りつつ、海外事業の拡大によって全体の収益性を高めるという特徴があります。



一条工務店の利益率と高品質住宅の両立方法
- 高性能を標準仕様で提供
- モデルハウスに注力した戦略
- 「権威付け」による信頼度向上
一条工務店は「家は、性能。」をスローガンに、高品質住宅と収益性の両立を実現しています。創業から一貫して性能を追求し、高機能・高性能住宅を標準仕様としている点が特徴です。断熱気密性の高さや全館床暖房などの高性能を、予算を問わず標準で提供することで差別化を図っています。
効果的な戦略として、モデルハウスの建築に注力している点が挙げられます。あえて大手ハウスメーカーが出展している展示場に進出し、競合にはない「自社の強み」を現場でアピールしています。「百聞は一見にしかず」の考えのもと、実際に体感できる場を提供することで受注につなげる戦略です。現在では住宅業界で出店棟数最多の企業となっています。
また、「省エネ大賞 経済産業大臣賞」「グッドデザイン賞」など多くの公的な賞を受賞することで「評価を見える化」し、信頼度を高めています。「権威付けマーケティング」をうまく活用し、テレビCMなどの大々的なプロモーションをほとんど行わなくても、年間1万件以上の注文住宅を手がける実績を築いています。利益率は業界平均と比べると4.9%程度とやや低めですが、高品質と適正価格のバランスを取りながら安定した経営を続けています。



ハウスメーカーの利益率比較と家づくりの選択肢


家づくりを始める際、ハウスメーカーや工務店の利益率を知ることは賢い選択につながります。各業態によって利益構造が異なり、それが住宅価格やサービス内容に影響しています。
- 建売住宅の利益率とハウスメーカーとの違い
- 下請け業者は儲かる?住宅建設における収益構造
- リフォーム事業の利益率と新築との比較
- ハウスメーカー選びで知っておくべき利益率の真実
- 地域別に見るハウスメーカーの利益率の違い
- 工法による利益率の違いと品質への影響
- 家づくりで失敗しないための業者選びのポイント
建売住宅の利益率とハウスメーカーとの違い
- 建売住宅の利益:1棟あたり500~600万円程度
- 注文住宅の利益率:大手ハウスメーカーで20~30%
- 建売住宅の価格設定:土地代+建物代(定額)+利益(定額)
建売住宅と注文住宅では、利益の構造が大きく異なります。建売住宅は1棟あたり500~600万円程度の利益を見込んで販売されています。興味深いのは、建売住宅の場合、物件価格によって利益額が変わるわけではないという点です。2500万円の物件でも5000万円の物件でも、利益額は同じく500~600万円程度に設定されていることが多いです。
一方、注文住宅の場合、大手ハウスメーカーでは20~30%の利益率が一般的です。例えば3000万円の注文住宅であれば、600万円~900万円が利益となる計算になります。建売住宅の価格設定は「土地代+建物代(定額)+利益(定額)」という構造になっており、同じ仕様の建売住宅で価格差がある場合は、主に土地代の違いによるものです。
建売住宅は薄利多売のビジネスモデルで成り立っており、数を売らないと利益が出にくい構造になっています。また、売れ残りが出ると価格見直しで値下げされることも多く、当初の利益額から大幅に減少することもあります。建売住宅会社は、時には赤字覚悟で販売することもあり、「どうしても今すぐに売りたい」という状況に陥ることもあるようです。



下請け業者は儲かる?住宅建設における収益構造
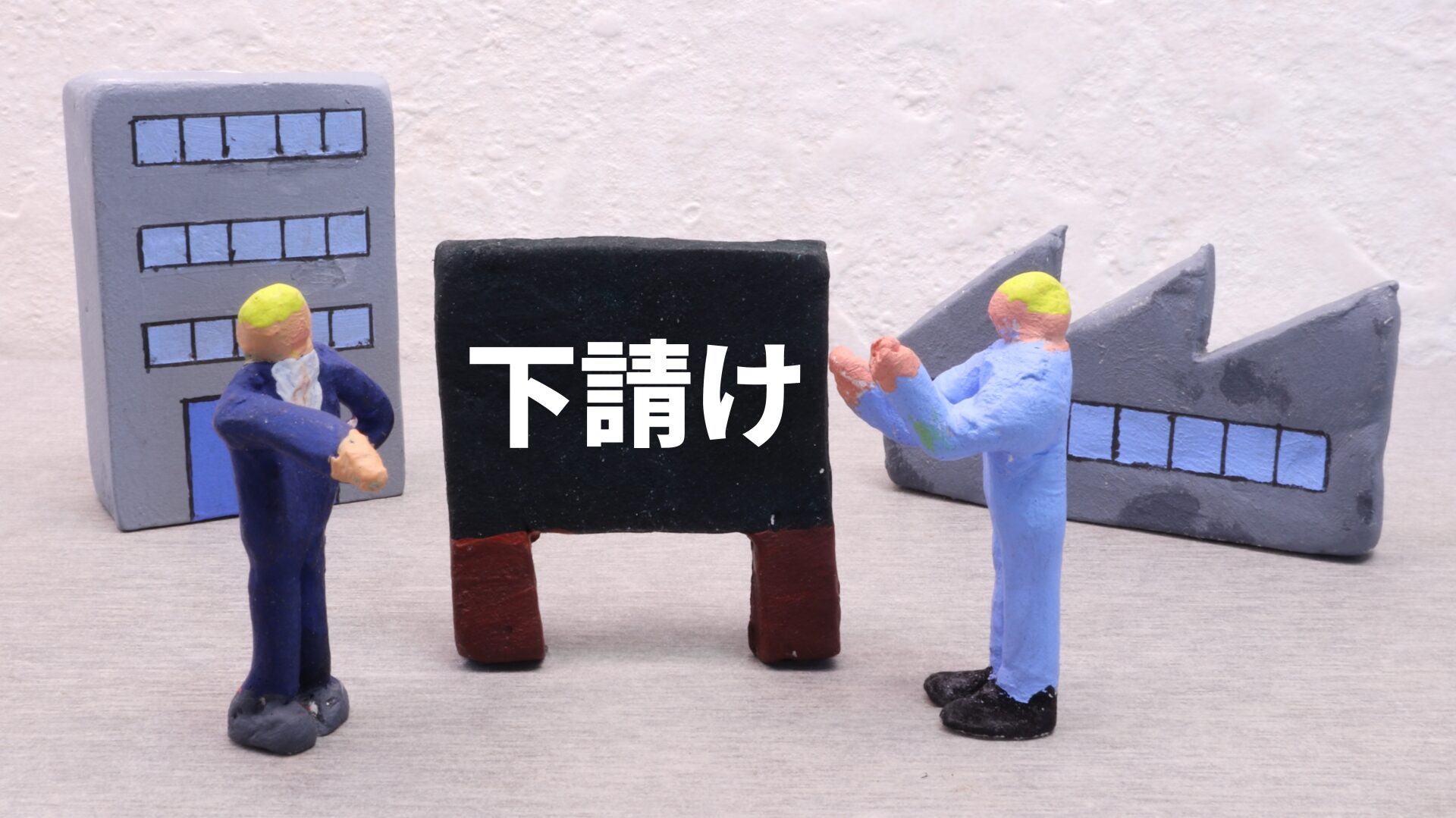
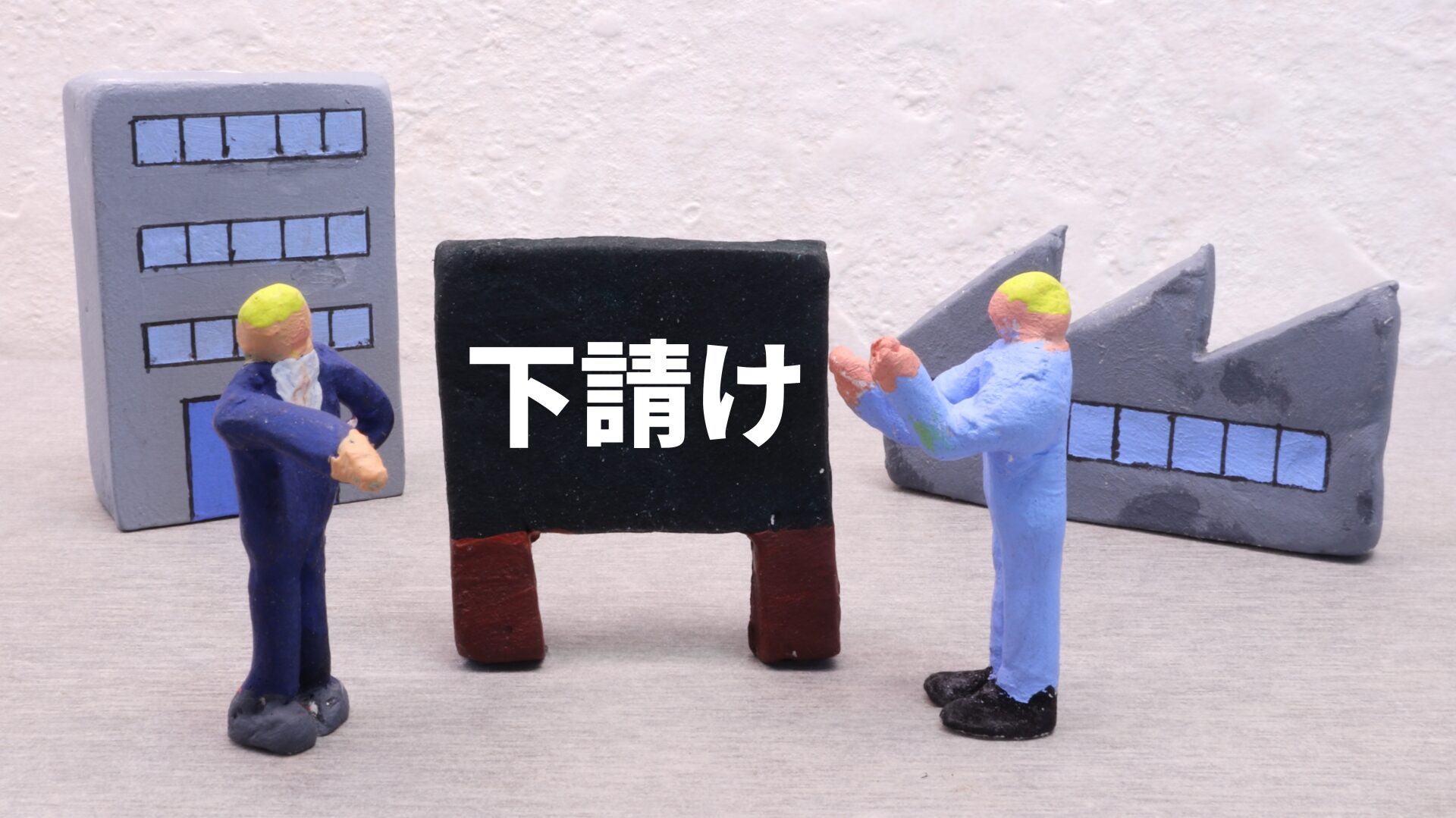
- 下請け業者の粗利益率:当初は10%程度が多い
- 改善後の粗利益率:工夫により30%まで向上可能
- 地域工務店の適正粗利率:30%程度(営業利益5%)
住宅建設における下請け業者の収益構造は、一般的に厳しいものがあります。下請け業務における粗利益率は当初10%程度と低く、多くの経営者が悩みを抱えています。しかし、適切な改善策を講じることで、粗利益率を30%程度まで向上させた事例もあります。
地域工務店の場合、適正な粗利率は大手ハウスメーカーの計算方法で言うと23%程度(地域工務店の計算方式では30%程度)とされています。そして販管費が18%、営業利益が5%というのが一つの理想的な形と考えられています。これは営業・設計・インテリアコーディネーター・現場監督・経理総務人事がすべて揃っている工務店の場合です。
設計部門や施工部門を持たない営業会社の場合は、営業利益率10%は確保したいところです。地域工務店が営業利益に目を向けるべき理由としては、1棟あたりの人件費がかかりすぎている可能性や、こだわりすぎた住宅は営業赤字になる可能性があること、ファミリー経営の場合は販管費の内容を理解しておく必要があることなどが挙げられます。



リフォーム事業の利益率と新築との比較
- リフォームの平均利益率:30%前後
- 新築住宅の理想的利益率:25%(実際は20%以下が多い)
- リフォーム利益率の幅:事業者によって20~40%と差がある
住宅業界において、リフォーム事業は新築よりも利益率が高い傾向にあります。リフォーム業の利益率(粗利)は平均30%前後と言われていますが、実態としては20%前後の事業者もいれば、40%の利益率を出す事業者もいます。一方、新築住宅の利益率は理想的には1棟あたり25%を目指したいところですが、現実的には粗利が20%を切ることがほとんどです。
リフォームの利益率が高い理由としては、何をすればどれくらいの費用がかかるのか基本的にはパーツの組み合わせ、つまり足し算で計算できることと、工事期間が短いことが挙げられます。新築は総額の予算があってできることを決めていくため、お客様の理想の住まいのために工務店が身を削る形で対応することが多く、粗利がどんどん削られてしまう傾向にあります。
リフォームの利益率を上げるためには、「値引きをされにくい環境を作る」「季節商材を扱う」「LTV(顧客生涯価値)を意識する」といった方法があります。特にクレジットカード支払いを提案すると不思議と値引きの話にならないという現象があり、多くのリフォーム事業者が実感しています。消費者は現金で支払う痛みよりも、クレジットカードで支払う痛みのほうが少ないため、値引き交渉が減少するようです。



ハウスメーカー選びで知っておくべき利益率の真実


- 大手ハウスメーカーの利益率:30~40%
- 工務店の利益率:20~30%
- 利益率が高い理由:広告費、展示場維持費、アフターサービス費用など
家づくりを検討する際、ハウスメーカーの利益率を知っておくことは重要です。大手ハウスメーカーの利益率は一般的に30~40%と言われており、地域密着型の工務店の利益率20~30%と比べると高めに設定されています。この違いは事業の運営方法やコスト構造によるものです。
ハウスメーカーは全国規模での営業活動や広告宣伝を行い、多くのモデルハウスや展示場を持っています。そのため、販売促進費や固定費がかかり、その分を利益率に上乗せする必要があります。一方で、工務店は地元に根付いた経営を行っており、大掛かりな広告宣伝を行わないことが多いため、その分のコストを削減できます。
利益率が高いからといって単純に「儲けすぎ」と判断するのは適切ではありません。利益率が高い企業は、コスト管理や効率的な運営の結果である場合が多いです。また、広告宣伝費や住宅展示場の維持費、アフターサービスなど、見えないコストも多く存在します。逆に利益率が低いということは、会社がうまく稼げていないという見方もでき、今後の事業の存続性に影響し、良質なアフターサービスを受けることが難しくなる可能性もあります。



地域別に見るハウスメーカーの利益率の違い
- 地域による価格設定:都道府県によって収入水準が異なる
- 利益率の地域差:同じハウスメーカーでも地域によって異なる
- 価格交渉の余地:地域の競合状況によって変動
ハウスメーカーの利益率は地域によって異なる傾向があります。大手ハウスメーカー各社は、地域や商品によって価格や利益率の設定を変えていることが多いです。これは、都道府県によって平均年収や生活水準が異なるためで、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、都道府県別の年収には大きな差があります。
ハウスメーカーはこうした地域の経済状況を考慮して、価格設定や利益率を調整しています。例えば、東京や大阪などの大都市圏では土地代が高いため、建物本体の価格を抑えめに設定する一方、地方では土地代が安いため、建物にかける予算を多めに設定できる傾向があります。
また、地域によって競合状況も異なります。競合が多い地域では値引き競争が起きやすく、利益率が圧迫されることがあります。逆に、特定のハウスメーカーのシェアが高い地域では、比較的高い利益率を維持できることもあるでしょう。家づくりを検討する際は、全国一律の価格設定ではなく、地域ごとの相場や競合状況を踏まえた交渉が可能かもしれません。



工法による利益率の違いと品質への影響


- 鉄骨系ハウスメーカー:利益率が比較的高い
- 木造系ハウスメーカー:利益率が比較的低い
- 工法別の利益率ランキング:鉄骨系が上位を占める傾向
住宅の工法によって、ハウスメーカーの利益率には大きな違いがあります。ハウスメーカーの売上高営業利益率ランキングの上位には、鉄骨系メーカーが多くランクインしています。例えば、積水ハウス(11.8%)やヘーベルハウス(10.3%)などの鉄骨系メーカーは、住友不動産(9.2%)や一条工務店(6.6%)といった木造系メーカーよりも高い利益率を誇っています。
この違いが生じる理由として、鉄骨の部品の原材料費が高いため、販売価格も比較的高額になり、結果として利益率も高くなる傾向があります。また、鉄骨系住宅は工場での生産比率が高く、規格化・標準化が進んでいるため、効率的な生産が可能となり、コスト管理がしやすいという特徴もあります。
一方で、工法による利益率の違いが品質に直結するわけではありません。例えば、木造系の一条工務店は利益率が比較的低めですが、高性能住宅の標準化とモデルハウス戦略により、高品質と適正価格のバランスを取りながら安定した経営を続けています。消費者としては、工法による利益率の違いを理解した上で、提供される品質やサービス内容、アフターサポートなどを総合的に判断することが重要です。



家づくりで失敗しないための業者選びのポイント
- 施工実績や口コミの確認
- 見積もり内容の明確さ
- 担当者との相性や対応力
- アフターサポートや保証内容
家づくりを成功させるためには、信頼できる業者選びが鍵となります。過去の施工事例や実績を確認することは、業者選びの基本です。施工棟数や創業からの年数、施工事例集から規模、価格、プランなど多彩な施工をしているかをチェックしましょう。また、直近5年ほどの棟数も確認し、安定した実績があるかを見極めることが大切です。
口コミや評判も重要な判断材料です。ネットや住宅雑誌の会社紹介ページ、完成現場見学会やOB訪問などに参加して、実際に建てた人から良い点や不満だった点を聞くことができれば、自分に合った建築会社かどうかを判断しやすくなります。紹介受注率という数値を持っている会社もあり、これは実際に建てた人などの紹介から受注を取れた割合を示すもので、満足度の高さを表す指標の一つです。
担当者との相性や対応力も見極めるべき重要なポイントです。人柄や話し方、自社の工法や特徴だけを語り続けるのではなく、「家づくりで何をしたいですか?」「どんな暮らしがしたいですか?」を聞いてくれる顧客目線の会社を選ぶことが大切です。電話対応、メール対応のスピード、プラン相談時の対応の早さや正確さなども対応力の見極めになります。



まとめ|ハウスメーカーの利益率を理解して賢い家づくりを
ハウスメーカーの利益率は業態や工法、地域によって大きく異なります。大手ハウスメーカーの粗利率は25~35%程度ですが、最終的な営業利益率は5~10%程度にとどまることが多いです。利益率の違いは以下のような要因によるものです。
- 大手ハウスメーカーと地域工務店では広告費や展示場維持費などの経費構造が異なる
- 鉄骨系は木造系よりも利益率が高い傾向がある
- 建売住宅は定額利益、注文住宅は比率で利益が決まる
- リフォーム事業は新築よりも利益率が高い傾向がある
利益率が高いからといって「儲けすぎ」と単純に判断するのは適切ではありません。高すぎる利益率は消費者にとって不利な価格設定の可能性がありますが、低すぎると企業の経営が厳しくなり、アフターサービスに影響が出る恐れもあります。家づくりでは利益率だけでなく、提供されるサービスや品質とのバランスを総合的に判断することが大切です。
家づくりを成功させるためには、スーモカウンターなどの中立的な相談窓口を活用し、複数の会社を比較検討することをおすすめします。